産学の問題意識が一致
まずはゲーム・インタラクティブアート専攻新設の経緯を伺えますか。
実は、事の起こりにはCG-ARTSさんが関わっています。2016年にCG-ARTSさんから、スクウェア・エニックスさんが藝大との人材育成を目的とした交流の機会を求めているとのお話をお伺いし、ご一緒にスクウェア・エニックスを訪問したのがきっかけでした。そこで当時スクウェア・エニックスのディレクターだった田畑さんをご紹介いただきました。『FINAL FANTASY XV』などを手がけられた方ですね。
田畑さんはゲーム制作にかかわる人材の育成について問題意識を抱えていました。近年のゲーム開発環境、特に映像技術の発達にともなって、アートの素養やスキルを持つ人材をこれまで以上に求めていると。いくらCGが発達しても例えばそこに説得力のあるボーン(骨格)を入れられないと魅力あるゲームはつくれない。いわば「ちゃんとデッサンができる」基礎の力に加え、ゲーム制作に求められる多様な能力を育てるため、藝大と連携できないかというお話でした。
当時、私自身も専攻のカリキュラムや卒業後の学生のキャリアについて問題意識を持っていました。1学年につきアニメーション研究科の定員は16名、アニメーションの領域ではおそらく世界一、二を争うくらいの優秀な人材が国内外から集います。にもかかわらず、就職率が非常に低いのです。在学中はとにかく制作に集中するため、就職活動はできません。また自身の表現をとことん追求させる教育方針なのですが、それがプロダクションワークに適した人材育成につながっているかというとそうではない。あまりにも産業と大学が離れすぎていると感じていたので、産業界からの打診は私にとっても非常にありがたいお話でした。
田畑さんをはじめ、スクウェア・エニックスのさまざまなクリエイターと話す中で感じたのは、産業界と私たちがいる教育界、アート界が目指すものの根底はとても似ているということです。商品か作品か、アウトプットの違いはあっても、目指す方向やプロセスは似通っている。教育プロセスにも産業界の視点が入ることで、よい化学反応が起きるのではないかと思いました。

「東京藝術大学ゲーム学科(仮)展」を開催しシミュレーション


アニメーション作品をゲームに展開
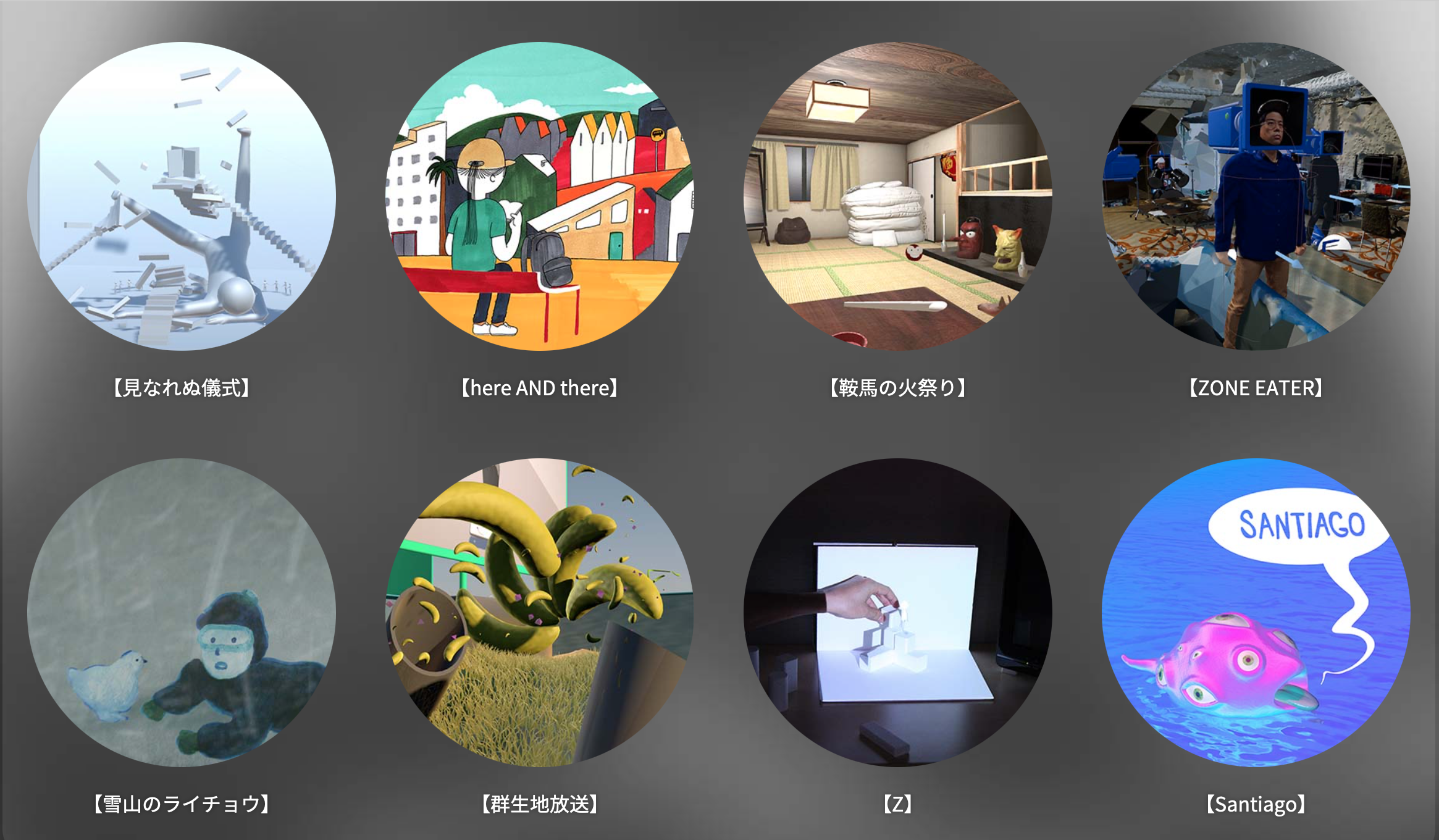
まずはコースを開設し外部メンターを招聘
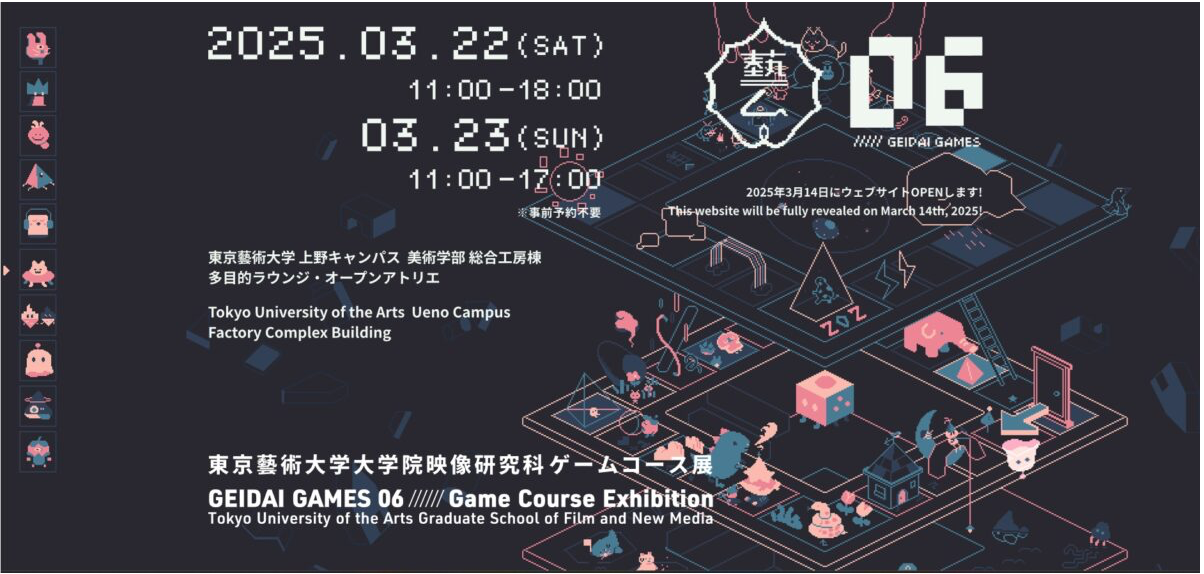


後編はこちら


